生きものの語り部が読んだ本を紹介する「読書案内」シリーズ。今回紹介するのは、2024年に出版された、打越綾子さんの『日本の動物政策』〔新版〕(ナカニシヤ出版)です。
※本書は2回にわけてご紹介します。今回は2回目。まだ1回目をお読みでない方は、ぜひそちらからご覧ください。
※1回目をお読みの方は、「注目ポイント」まで飛んでください。
著者紹介
打越綾子さんは、1994年東京大学法学部卒、2002年に同大学大学院で博士(法学)を取得し、行政学・地方自治論を専門に、成城大学で教壇に立ってきた先生です。
政策学や地域自治に軸足を置きつつ、特に愛玩動物、野生動物、動物園動物、実験動物、畜産動物に関する法制度や政策、各地域の取り組みを幅広く扱う、動物政策の第一人者です。
打越さんは、成城大学の公式ウェブサイトやSNSでも紹介されている通り、避暑地として有名な軽井沢町にお住まいです(2025年6月現在)。そのため、長野県での野生動物対策や、小諸市動物園の再生などに貢献することができています。
どんな人におすすめ?
この本は、
- 動物のことを大切にしたいと思う人
- ペット、野生動物、野良猫などが嫌いな人
- 行政職員・自治体関係者
- 多様な動物に関しての法制度、政策、行政の取り組みを知りたい学生、研究者
におすすめです。
動物政策に限ったことではないと思いますが、現状や政策について全く逆の意見を持っているAとBがいることがあります。そのときにAは「Bが○○しないのは間違っている」、Bは「Aの××という主張は度がすぎている」などと互いに対立することが多いです。
本書で一貫して見られる打越さんの考え方は、こうした対立構造が存在するなかでも、どのように対話・協働を生み出すのかが重要であるということです。
批判するのは簡単です。しかし、自分にできることはなにか、相手はどのような立場に置かれているのかを考えてふるまうことが大切だと、本書を読み終えて、あらためて実感することになるでしょう。
注目ポイント
1回目の特集で、『日本の動物政策』は主として、終生飼養動物と非終生飼養動物の2つにわけて述べていると説明しました。(まだお読みでない方は、ぜひお読みください!)
今回は、そのうち非終生飼養動物について考えてみましょう。
非終生飼養動物とは、「終生飼養」を原則とする動物愛護管理法において、例外的に終生飼養の対象とならない動物を指します。具体的には、「実験動物」と「畜産動物」が想定されています。これらの動物は、研究や生産といった目的のために飼養されています。つまり、「人間のための死」が予定されて生まれてくるわけです。
そして、そうした動物たちは、本ブログが扱う動物園とも、けっして関係ないわけではありません。
- 動物たちが怪我をしたり病気になった時に治療で使う薬は、多くの実験動物の犠牲を経て開発されました。
- 動物の繁殖についての知識は、畜産動物の繁殖で用いられてきた技術が応用される場合があります。
- 動物たちのエサは、馬肉、鶏頭などの(古典的な意味ではないにせよ)畜産動物です。
ほかにも挙げればキリがないでしょう。かといって「これだから人間はひどい」、「動物たちがかわいそう」と言って、過激な主張を続けても、それは真の意味で動物のためにはならないでしょう。
人間が動物を利用し、貴重な命を取ってでも、繁栄する。この長年つくりあげられてきた関係は、ひとことで片付けらえるようなテーマでありません。
だからこそ『日本の動物政策』を読んで、みなさんには実感を持って考えてみてほしいんです。
まとめ
今回の記事では、打越綾子さんの『日本の動物政策〔新版〕』の【読書案内】(2)をお届けしました。
今後も当ブログでは、生きものの語り部が読んだ本をご紹介していきます。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!

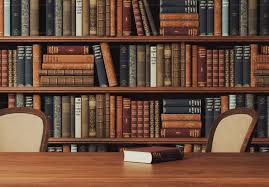



コメント